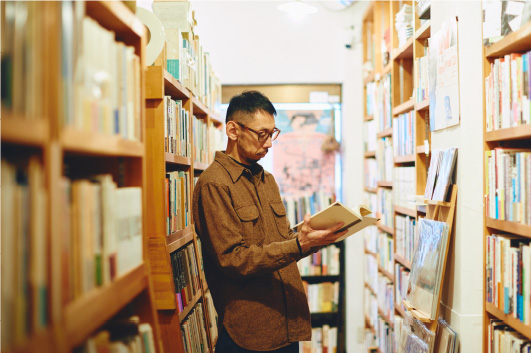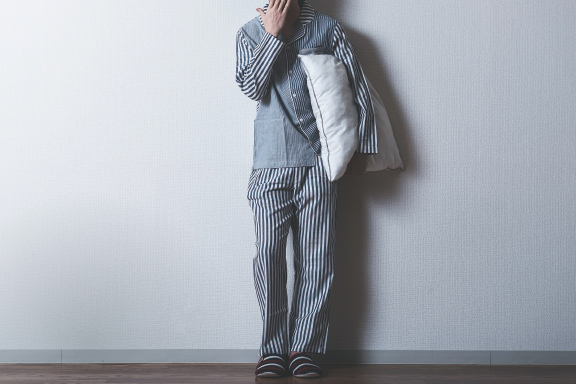#046
#046#040いとしい梅酒。
かねこふぁ~む

初夏のわずかなひとときだけ店先に並び、さわやかな色と香りで梅雨の訪れを告げてくれる梅の実。梅酒、梅ジュース、梅干しと梅の実を使った手作りの作業は「梅仕事」ともいわれ、毎年楽しみにしている方も多いことでしょう。一般的に、シーズン初めに出回る青梅は梅ジュースや梅酒に、やや遅れて並び始める熟した梅は梅干しに適しているといわれます。短い旬を逃さずにおいしく仕上げるコツを伺うため、神奈川県横浜市にある果樹農園「かねこふぁ~む」を訪ねました。

のどかな里山の麓にある「かねこふぁ~む」は、梅、柿、キウイ、ぶどう、柑橘、露地野菜など季節ごとに様々な果樹・野菜を栽培している農園。梅の時期には、梅の収穫体験や梅干し講座、梅の加工品販売なども行っています。出迎えてくださった金子洋子さんは、長年あらゆる梅の加工品の試行錯誤を重ねてきたという、いわば梅の達人。金子さんは、収穫体験を希望される方にはまず何をつくりたいかを確認し、おすすめの時期をアドバイスしているのだそう。

「梅ジュースなら、青々として固い梅の方がエキスがよく出ます。梅干しはやっぱり枝から落ちる寸前の完熟しているものがおすすめです。でも梅酒の場合は、実は青梅と熟した梅と両方でつくれるんですよ。青梅でつくった梅酒はすっきりとした飲み口で、見た目もクリアな色をしています。完熟梅でつくると、すごくフルーティーな梅酒になって、秋頃にはきれいな琥珀色になるの。それぞれの味わいがあるので、ぜひ両方つくって飲み比べてみてください」。

青梅の時期を逃してしまった時は、完熟梅で違った味わいの梅酒をつくってみるのもいいかもしれません。ただし、あらゆる梅仕事に共通して気をつけてほしいポイントがある、と金子さん。
「梅を入手したら、できるだけ早く加工すること。梅は収穫すると、1日で約3%ずつどんどん水分が飛んでしまうんです。梅がもぎたての新鮮なものであるほど、梅酒や梅シロップの水の上がりもよくなります。完熟梅でつくる場合も、自分で追熟させるのではなく、木で十分熟した物を収穫してすぐ使うのがおすすめです」。

さらに梅仕事は、出来上がった物を飲む・食べる以外にもいろんな楽しみがあるのがいい、と金子さんは笑います。
「梅酒なら、漬けてから飲めるようになるまでの待っている時間がいいんです。びんの中でゆっくりと梅が変化していく様子を、毎日眺めるの。まるで育てているみたいで、愛着がわきますよ。それから私が好きなのは、作った梅酒をおすそ分けすること。きれいな空きびんに詰めて、オリジナルのラベルを作ったり、ラッピングしたりする手間が楽しいんです。あとはいろんなお酒で梅酒を漬けてみたり、梅酒の梅を混ぜ込んでケーキを焼いてみたり……毎年実験みたいに楽しんでいます。これはやっちゃいけないなんてことはないですから、自分なりにいろんなアレンジを試してみるといいですよ」。
おいしくていつの間にかいとしくなる、自分だけの梅仕事を楽しんでみませんか。

かねこふぁ~む流レシピのご紹介

かねこふぁ~む流・梅酒レシピ
- 用意するもの
- 青梅または完熟梅 2kg
- ホワイトリカー 1.8L
- 竹串
- 氷砂糖 1kg
- 5Lのビン

かねこふぁ~む流・梅ジュース
- 用意するもの
- 青梅 2kg
- 酢 100ml
- 竹串
- 氷砂糖 1.5kg
- 5Lのビン

梅酒も梅ジュースも、梅と氷砂糖が1:1ではなく、氷砂糖をやや少ない割合にしているのが金子さん流。これは梅の重量の約3分の1は種の重さであることを考慮したもので、その分の砂糖を減らすことでよりすっきりとした味わいに仕上がるのだそうです。
使った梅の実は、一緒にグラスに入れたり
そのままでも美味しくいただけます。
ジュースは冷蔵庫で保存しましょう!


取材協力:かねこふぁ~む
果樹・野菜の栽培のほか、直売や加工品の製造・販売も行っています。果樹の品質や畑の管理状況などを審査する「神奈川県果樹立毛共進会」のウメ部門で2024年度の最優秀賞を受賞。敷地内には金土日のみオープンするカフェも併設しており、金子さん手作りの梅ジュースやケーキなどをいただけます。
かねこふぁ~む 公式WEBサイト
ARTICLE
 #046
#046