

ジメジメとした湿気は、日本の気候ならではの悩み。特に新築の家を建てる際には、湿気対策をしっかりと考えておくことが大切です。湿気は、カビやダニの発生、建材の腐食など、家の寿命を縮めるだけでなく、ご家族の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、新築の家を建てる際に効果的な湿気対策について、設計から建材選び、入居後の対策まで詳しく解説します。快適で健康的な住まいを実現するために、ぜひ参考にしてください。
▼関連記事もあわせてご覧ください。
「夏型結露」を徹底解説!原因と対策をマスターしよう
対策必須!湿気のリスクとは?

快適な暮らしを脅かす湿気。そのリスクを甘く見てはいけません。目に見える被害だけでなく、気づかないうちに進行する深刻な問題も潜んでいます。長く暮らす家だからこそ、家づくりの段階での対策が重要です。
1.カビ・ダニの発生
高温多湿な環境は、カビやダニの温床となります。壁や天井、家具の裏などに発生したカビは、アレルギーなどの健康被害の原因となるだけでなく、建材を劣化させる原因にも。ダニも同様にアレルギーを引き起こし、喘息などの呼吸器疾患のリスクを高めます。特に小さなお子様やアレルギー体質の方は、注意が必要です。
カビやダニの発生を防ぐためには、湿度を適切にコントロールすることが重要です。こまめな換気や除湿機を活用し、清潔な住環境を維持しましょう。
2.体調不良や熱中症のリスク
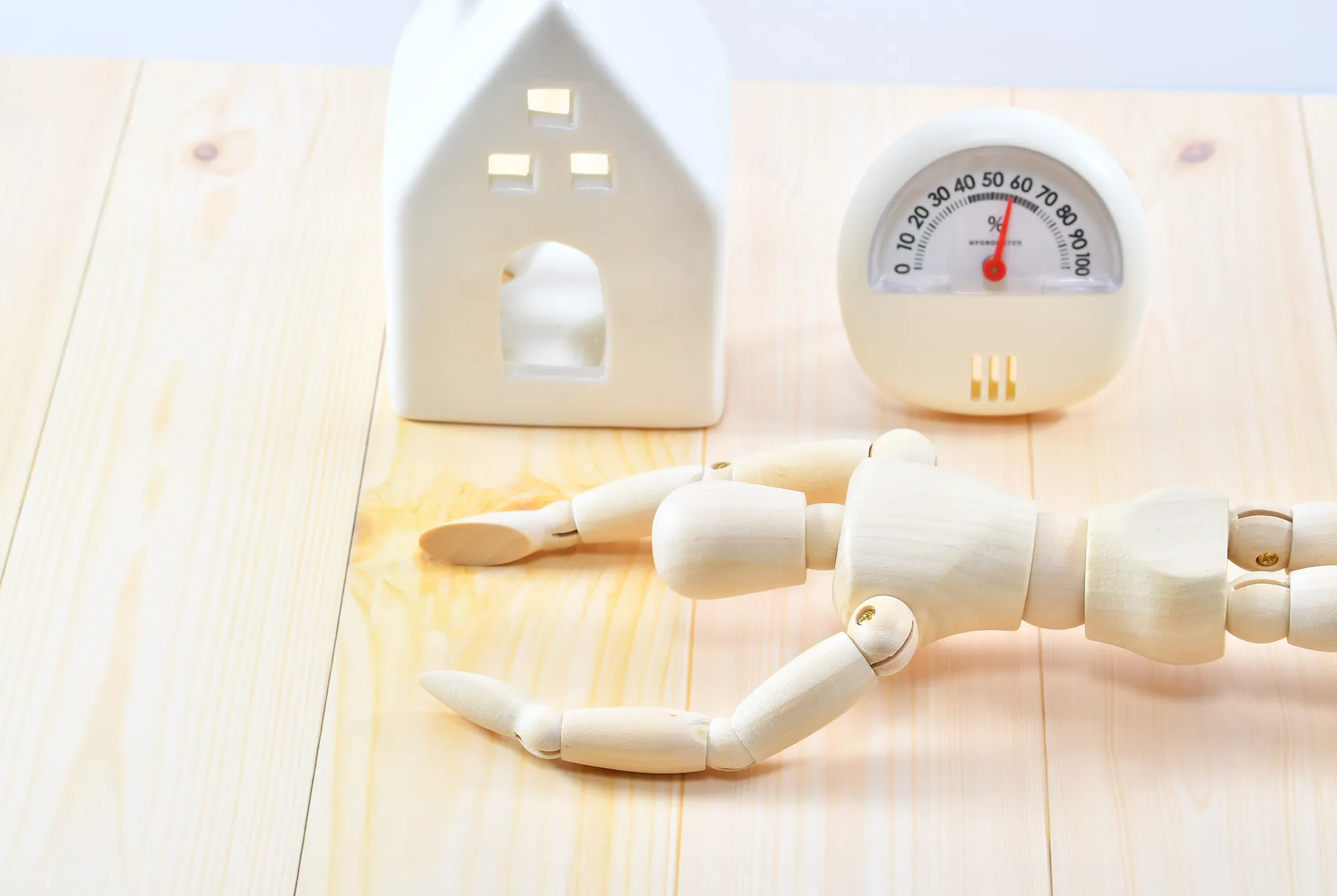
湿度が高いと、汗が蒸発しにくくなり、体温調節がうまくいかなくなります。そのため、夏場は熱中症のリスクが高まり、冬場は体感温度が下がって風邪を引きやすくなることも。また、ジメジメとした環境は、自律神経のバランスを崩し、だるさや頭痛、睡眠不足などの原因となる場合もあります。
快適な室温と湿度を保つことは、健康的な生活を送るうえでとても大切なこと。新築時に対策しておくことはもちろん、住み始めてからもエアコンや除湿機、加湿器などを適切に使用し、一年を通して快適な室内環境を保つように心がけましょう。
3.光熱費の増加
湿度が高いと、冷房や暖房の効率が悪くなります。特に夏のジメジメした時期は、気温のわりに涼しく感じにくいため、ついついエアコンの設定温度を下げてしまい、電気代が増えてしまいます。梅雨や夏場は、エアコンの除湿機能だけでは十分でなく、除湿機を併用することも少なくありません。
このように、湿気によって冷房効率が低下することで、余計なエネルギーを使ってしまうのです。適切な湿気対策ができていない住宅は、快適さを損なうだけでなく、家計にも大きな影響を与えてしまいます。
4.建材の腐食
高湿度な環境下では、壁の内部や窓の周辺で結露が生じやすくなります。この結露によって建材が長時間湿った状態に置かれると、腐食や劣化が進行し、住宅の耐久性を損なう原因となります。加えて、湿気を含んだ木材はシロアリにとって最適な生息場所となるため、シロアリによる被害を招きやすくなります。
これらのリスクを回避するためにも、早めに適切な湿気対策を講じておきましょう。
設計段階でできる湿気対策

住まいの湿気対策は、家づくりの最初の計画段階が大切です。土地選びに始まり、間取りの工夫、そして換気システムの選定まで、しっかり対策するかどうかで、住み心地が大きく左右されます。
ここでは、住まいづくりを考える上で、設計時に意識しておきたい重要なポイントを解説します。
1.水はけと風通しの良い敷地選び
新築住宅における湿気対策の第一歩は、敷地選びにあります。水はけの良い土地であれば、雨水が速やかに排水され、地盤や建物の基礎部分への湿気の影響を最小限に抑えることができます。さらに、周囲に高い建物や山などがなく、風通しの良い立地を選ぶことで、建物内に湿気がこもるのを防ぎ、カビやダニの発生リスクを低減できます。
土地を選ぶ際には、雨天後の水たまりの状況や、風の通り道、周辺の環境などをよく確認し、長期にわたり快適に暮らせる住環境かを見極めることが大切です。
2.高気密・高断熱な家づくりで湿度をコントロール
湿気に強い家を選ぶなら、高気密・高断熱の住宅がおすすめです。建物の気密性と断熱性を高めることで、外部からの不要な空気や湿気の侵入を抑制し、室内の温度と湿度を安定させることができます。これにより、冷暖房効率が向上し、エネルギー消費を抑えながら快適な住環境を維持することが可能になります。
ただし、高気密住宅においては、計画的な換気が不可欠です。換気が不十分な場合、室内に湿気や汚れた空気が滞留しやすくなるため、適切な換気システムの導入を検討しましょう。
3.日当たりと通風を考慮した間取り設計

間取りの計画においては、自然の日光と風の流れを最大限に活かすことが、快適な住まいづくりに直結します。南向きにリビングを配置したり、大きな窓を設けたりすると、室内にたっぷりと自然光を採り込め、湿気がこもるのを防ぎます。
また、風の通り道を意識して、窓を対角線上に配置したり、片開き窓の開き方向にも配慮したりすると、効率的に風を室内に取り込めるでしょう。特に、湿気が溜まりやすい水回りや収納スペースには、積極的に窓や換気口を設けると、結露やカビの発生リスクを低減できます。
4.効率的な換気計画
現在の日本の建築基準法では、新築住宅への24時間換気システムの導入が義務付けられています。これにより、新築される住宅は、一般的に「1時間に室内の空気の半分」が入れ替わるように設計されています。しかし、単に換気を行うだけでは、外部の温度や湿度の影響を室内に受けやすくなる点に注意が必要です。
特に、外部と室内の温度差が大きくなる夏や冬は、外気をそのまま取り込むと冷暖房効率が低下し、居住者の快適性や光熱費に影響を与えます。そのため、外気の影響を最小限に抑えながら、効率的に室内の空気を入れ替えることができる換気システムを選ぶことが重要になります。
例えば、細田工務店の注文住宅で採用している「熱交換換気システム」は、室内の温度や湿度をできるだけ変化させずに、新鮮な空気を取り込めるのが特長です。従来の換気システムと比較して、外気の温度や湿度の影響を受けにくいため、梅雨時期や真冬でも室内の快適な状態を維持しやすいのです。
「熱交換換気システム」を採用している浜田山モデルハウスを見学する
建材選びでできる湿気対策

住宅の湿気対策は、設計段階だけでなく、実際に使用する建材にも大きく左右されます。ここでは、住まいの快適性や家族の健康に直接関わる、建材選びの重要なポイントを紹介します。
1.【断熱材】湿度をコントロールする断熱材を選ぶ
断熱材は、外の空気の影響を遮り、室内の温度を安定させるために欠かせない建材です。温度が一定に保たれることで相対湿度の急激な変動も抑えられ、結果として湿度も安定しやすくなります。
さらに近年は、従来の断熱材に加えて、湿気を吸ったり吐いたりする「調湿機能付き断熱材」が使われるようになってきました。これらの断熱材は、室内の湿度が高い時には余分な湿気を吸収し、乾燥している時には蓄えていた湿気を放出するため、結露を防ぎ、カビやダニの増殖リスクを大きく減らせます。
例えば、セルロースファイバーや羊毛など、自然素材を使った断熱材は、環境にも優しく、長い期間にわたって高い調湿効果を発揮します。新築の家でこれらの断熱材を積極的に採用すれば、心地よく健康的な住環境が叶うでしょう。
一方で、グラスウールなどの繊維系断熱材を使用する場合には、断熱材内部への湿気の侵入を防ぐため、防湿フィルム施工などの防水対策を正しく行うことが重要です。
細田工務店の注文住宅では、水を使って現場で発泡させる硬質ウレタンフォーム断熱材を使っています。湿気を通しにくく、結露に強い特徴があります。
「硬質ウレタンフォーム断熱材」を採用しているモデルハウスを見学する
2.【壁・天井材】湿気を吸収しやすい素材を選ぶ

壁や天井の材料には、湿気をほどよく通し、室内の環境を快適に保つ「透湿性」の高い素材を選ぶと良いでしょう。透湿性に優れた代表的な素材には、漆喰や珪藻土などの自然素材があります。これらの素材は、室内の湿度が高い時に余分な湿気を吸い取り、乾燥している時には湿気を放出する調湿効果を持っています。
また、最近ではビニールクロスでも、湿気を吸ったり吐いたりする機能や通気性を持つ製品がたくさん出てきています。これらの素材を、洗面所やトイレ、玄関や廊下など、湿気がこもりやすい場所に使うと、家全体の快適さが向上するでしょう。
細田工務店の小金井モデルハウスでは、100%天然素材の「チャフオール」をLDKや玄関ホールの壁に採用しています。「消臭性」「吸放湿性」「抗菌性」に優れています。
「チャフオール」を採用しているモデルハウスを見学する
3.【内装材】調湿・脱臭効果のある素材を選ぶ
エコカラットなどの内装用の調湿壁材は、見た目の美しさだけでなく、機能性にも優れています。調質機能があり、室内の湿度が高いときは湿気を吸収し、乾燥しているときは湿気を放出します。結露やカビの発生を抑える効果があり、快適な室内環境を保てます。
脱臭効果もあるので、トイレ、玄関、ペットのいる部屋などに採用するのも効果的です。
多彩なデザイン・カラー・質感があり、インテリアのアクセントとしても優秀なので、希望のテイストにあったものを選んでみましょう。

4.【床材】調湿・防カビ効果のある床材を選ぶ

床材は、室内の湿気をコントロールするうえで意外と重要な役割を果たしています。
例えば無垢フローリングは、天然木ならではの調湿性能を持ち、空間全体の湿度バランスを自然に整える効果があります。さらに、最近では防カビ加工が施されたフローリング材や、調湿機能を強化した床材も登場しており、より効果的な湿気対策ができるようになっています。
特に、洗面所やキッチン、脱衣所など水回りの床には、防水性・防カビ性に優れた床材を選ぶことでカビや腐食のリスクを軽減できます。適切な床材を選ぶことは、建物全体の耐久性や快適性を高めることにつながります。

5.【窓】断熱性と気密性の高い窓を選ぶ

窓は外の環境の影響を最も受けやすい部分であり、断熱性・気密性の高い窓を採用することで、外の湿気や温度変化をしっかりと遮断できます。
結露の発生を抑えるためには、ペアガラスやトリプルガラスといった複層ガラス窓や、断熱性能に優れた樹脂サッシが特におすすめです。これらの窓は、室内の温度と湿度を安定させるだけでなく、冷暖房効率の向上や光熱費の節約にもつながります。
また、玄関ドアも断熱性や気密性に考慮して選びましょう。高性能な玄関ドアを採用すると、室内に冷たい空気や熱気が入るのを防ぐとともに、玄関や廊下と居室の温度差を小さくし、ヒートショック対策にもなります。
「二重サッシ+樹脂フレーム」を採用しているモデルハウスを見学する
新築でも油断禁物!入居後の湿気対策

せっかく設計や建材でしっかり湿気対策をした新築住宅でも、住み始めてからのちょっとした油断が、湿気によるトラブルにつながることがあります。ここでは、入居後に気をつけたい湿気対策のポイントを確認しておきましょう。
1. 24時間換気は停止しないのが基本
新築住宅には24時間換気システムが設置されています。ところが、「寒いから」「電気代が気になるから」と、つい換気を止めてしまう人もいるようですが、それはNGです。換気システムを止めてしまうと、室内の湿気や空気中の有害物質が滞留し、カビやダニが発生するリスクがぐんと高まります。
健康で気持ちの良い暮らしを長く続けるためには、24時間換気は必ず運転させ続けましょう。換気の仕組みをきちんと理解し、正しく使い続けることが湿気対策の基本中の基本です。
2. 窓の開けっ放しには要注意
部屋の空気を入れ替えるために窓を開けるのは良いことですが、開けすぎには気をつけましょう。特に梅雨や雨の日は外の湿気が多く、窓を開けっ放しにすると室内の湿度が上がり、カビやダニ発生の原因になります。加えて、外から花粉やホコリも入りやすくなるため、健康面でも注意が必要になります。
効果的に換気するには、短時間だけ窓を開けて空気を入れ替えるか、サーキュレーターを併用して空気の流れを作ると良いでしょう。窓の開け方や開けている時間は、天候や時間帯に合わせて調整し、余計な湿気を部屋に入れないようにしましょう。
3. サーキュレーターや除湿機、シーリングファンを上手に活用

部屋の空気が停滞しがちな季節や、洗濯物を室内に干すことが多い家庭では、サーキュレーターや除湿機を使うことをおすすめします。サーキュレーターで室内の空気を循環させることで、壁や窓にできる結露を減らし、カビの発生を抑えられます。
また、吹抜けや天井の高い家では、シーリングファンを採り入れるのも良いでしょう。シーリングファンは天井付近に溜まりやすい暖かい空気や、下に溜まった湿気を効率よく循環させ、室内全体の温度・湿度を均一に保つのに役立ちます。インテリアに合うものを選べば、空間のおしゃれなアクセントにもなります。
4. 定期的な清掃と点検を忘れずに
湿気がたまりやすい収納スペースでは、物をぎゅうぎゅうに詰め込まず、少しスペースを空けておくことが大切です。収納物は時々取り出してホコリやカビがないか確認し、必要に応じて拭き掃除をしたり、乾燥させたりしましょう。また、換気口のフィルターには湿気やホコリがたまりやすいので、定期的に取り外して清掃してください。
これらのこまめな手入れや点検を習慣にすると、湿気やカビの発生を予防し、快適な住まいを長く維持できます。
新居での快適な暮らしのために、湿気対策を万全に!

新築のマイホームは、家族にとってかけがえのない場所。だからこそ、いつまでも心地よく過ごせるように、湿気対策はしっかりとしておきたいものです。
これまで見てきたように、湿気対策は設計による工夫や建材選び、新居での住まい方など色々な面から考える必要があります。自分たちに合った対策を見つけるためには、専門家の知識と経験が頼りになります。
細田工務店では、お客様一人ひとりのライフスタイルやご要望に合わせて、最適な湿気対策をご提案しています。高気密・高断熱住宅の設計・施工はもちろん、無垢床材といった自然素材を活かした家づくりや、熱交換換気システムの導入など、さまざまな方法で湿気対策をサポートいたします。
経験豊富なスタッフが、土地選びから間取りの設計、建材選び、そして住み始めてからのアフターフォローまで、責任を持って対応いたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。












